最初に
赤ちゃんを産むための産院(産婦人科、産科、分娩施設)は、施設によっていろいろな特徴や違いがあり、自分にあったところを見つけることが大切です。妊娠から出産までの間には妊婦検診や相談などで10数回程度、産院に通うことになります。さらに、赤ちゃんの発育・健康の確認や母体の定期検診、産後プログラムへの参加などにより、出産後も長く付き合うことになる可能性があります。
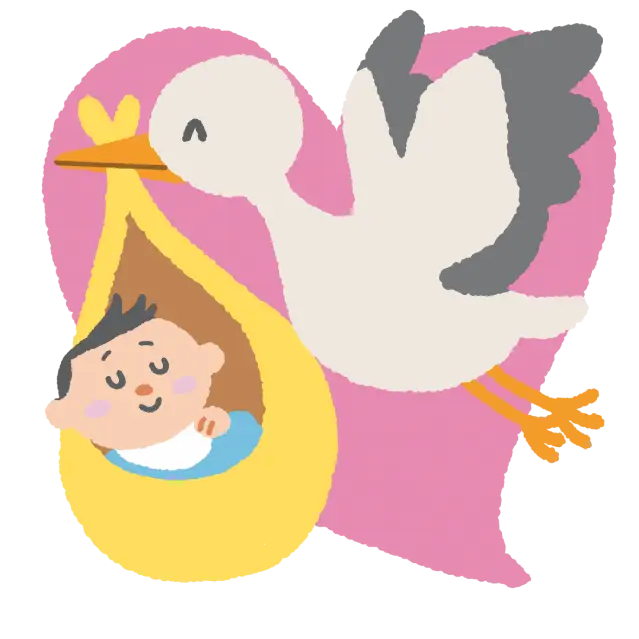
「産科」と「婦人科」の違いは?
産婦人科の診療科目には「産科」と「婦人科」があり、いずれかの専門施設もあります。産科は主に妊娠・出産や産後について、婦人科は女性特有の疾患(子宮・卵巣の病気、性感染症、更年期障害、避妊・中絶、不妊など)についての相談・診療を行います。
また、お産の選択肢としては助産院もありますが、医師がいないため医療行為を行うことはできません。そのため、助産院での出産はリスクの少ない正常妊娠経過であることが条件となります。
このように産婦人科は、出産だけでなくライフステージごとの女性の健康に寄り添う場所でもあります。だからこそ、生涯を通じて相談したいと思えるような施設を選んでもらえれば、なによりです。そこで今回は、自分に合った産婦人科について考える上でのポイントをいくつかご紹介します。
産院選びのポイント
「通いやすさ」で考える
一般的に妊娠初期から23週(約6カ月)までの検診は月1回程度ですが、24週から35週(9カ月)には2週間に1回、それ以降は週1回と徐々に回数が増えていきます。そのため、自宅や職場からの距離や移動手段など、通いやすさも産院選びのポイントです。加えて、出産期(陣痛時)の安全を考えるなら自宅から30分以内に到着できる施設が望ましいでしょう。

「スタッフ・サポート体制」で考える
産科の主なスタッフは医師、助産師、看護師、薬剤師、栄養士、ソーシャルワーカー(MSW)など。人員や各スタッフとの関わり方は施設によって異なりますが、これらのスタッフがチームで出産をサポートします。また、妊婦さんの相談窓口として助産師外来を開設しているところもあります。
これに加えて、総合病院には小児科や内科をはじめ、あらゆる診療科が併設されているので、合併症がある場合や分娩時に緊急事態が起こった場合も速やかに適切な処置を受けることができます。

「設備・サービス」で考える
出産は女性の人生における大切なイベントでもあります。そんな特別な期間を過ごす施設だからこそ、雰囲気や設備などにこだわりたいという方もいるでしょう。基本的な出産メニュー以外のプラスαのサービスとして、マタニティヨガ、マッサージといった産前・産後のケアプログラム、入院する部屋や食事、アメニティ、出産のお祝い品などで考えるのも選択肢のひとつです。

「バースプラン(出産方法)」で考える
バースプランとは、どのように出産したいのか、出産に対する自分の考え方や希望・要望をまとめたものです。具体的には、自然分娩や無痛分娩、フリースタイル分娩(分娩台にしばられない自由な姿勢でのお産)、LDR(陣痛から分娩、産後の回復までの一連を1カ所で行える個室)の使用、家族の立ち合い、産後の母子同室・別室の希望など。施設によって対応できること、できないことがあるので、事前にバースプランを伝えて相談することも大切です。

「出産費用」で考える
一般的な健康保険(国民健康保険、健康保険組合、全国健康保険協会(協会けんぽ)や共済組合)に加入している方は出産育児一時金として赤ちゃん一人につき50万円が支給されます。分娩費用の設定は施設によって異なり、出産育児一時金の金額で出産費用の全額がカバーできる=自己負担のない設定としている施設もあれば、あらかじめ自己負担が発生する設定としている施設もあります。また、無痛分娩をご希望の場合、麻酔費用は別途自己負担となる場合がほとんどで、金額は施設ごとにばらつきがあります。産前、産後は何かとお金がかかる時期でもありますので、必要となる費用はあらかじめ確認しておきましょう。
「産後ケアサービスの有無」で考える
出産後、大変な時期のお母さんと赤ちゃんをケアする「産後ケアサービス」。多くの自治体で費用の助成を行っていることもあり、利用する方も増えています。もし産後ケアサービスの利用をご希望の場合、サービスを実施している施設であれば移動の手間など無く分娩後に継続した利用が可能です。分娩後、時間をおいてから利用する場合でも産前、産後の経過を知っている顔見知りの医療スタッフによるケアを受けることが出来ます。
まとめ
産院選びのポイントお分かりいただけましたでしょうか?出産という素晴らしいライフイベントをより良いものとするため参考にしていただけると幸いです。施設見学会や説明会を実施している施設も多くあります。いくつか参加してみると各施設ごとの特色や方針がさらに見えてくると思います。ぜひそうしたイベントへ参加してみることもおススメします。


